|
嘆岄愇偼慄偺岎傢偭偰偄傞強偵抲偔 嘇崟愇丄敀愇岎屳偵弴斣偵懪偮 嘊堦搙抲偄偨愇偼摦偐偣側偄 |
 丂埥傞梒抰墍偱偼偙傟傪乽嶰偮偺偍栺懇乿偲偟偰巕嫙偨偪偵偍榖偟偟偰偄傑偡丅墍帣偱傕偙傟偼偡偖棟夝偟傑偡偺偱丄愢柧偵帪娫偼偐偐傝傑偣傫丅
丂埥傞梒抰墍偱偼偙傟傪乽嶰偮偺偍栺懇乿偲偟偰巕嫙偨偪偵偍榖偟偟偰偄傑偡丅墍帣偱傕偙傟偼偡偖棟夝偟傑偡偺偱丄愢柧偵帪娫偼偐偐傝傑偣傫丅| 嘋愇傪埻偆 |
 丂巹偑巕嫙偨偪偵嫵偊偼偠傔偨帪丄傑偢侾恾偺宍傪帵偟偰乽偙傫側傆偆偵埻傔偽崟愇偑庢傟傞傫偩傛乿偲愢柧偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄偙傟偱偼巕嫙偨偪偺棟夝搙偑掅偄偙偲偵婥偯偒傑偟偨丅偙偺愢柧偱巕嫙偳偆偟懳嬊偝偣偰傒傞偲丄傎偲傫偳偺巕嫙偨偪偑愇傪埻偆偙偲偑偱偒偰偄傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱丄弶傔偐傜宍傪帵偡偺偱偼側偔丄巕嫙偨偪偵傗傜偣偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅
丂巹偑巕嫙偨偪偵嫵偊偼偠傔偨帪丄傑偢侾恾偺宍傪帵偟偰乽偙傫側傆偆偵埻傔偽崟愇偑庢傟傞傫偩傛乿偲愢柧偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄偙傟偱偼巕嫙偨偪偺棟夝搙偑掅偄偙偲偵婥偯偒傑偟偨丅偙偺愢柧偱巕嫙偳偆偟懳嬊偝偣偰傒傞偲丄傎偲傫偳偺巕嫙偨偪偑愇傪埻偆偙偲偑偱偒偰偄傑偣傫偱偟偨丅偦偙偱丄弶傔偐傜宍傪帵偡偺偱偼側偔丄巕嫙偨偪偵傗傜偣偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅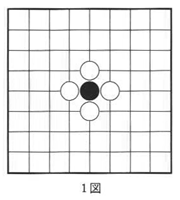
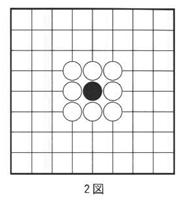
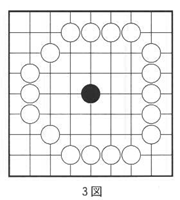
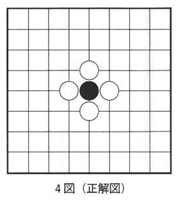
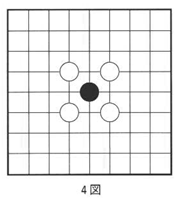
| 嘍億儞僰僉僎乕儉乮愇庢傝僎乕儉乯 |
 丂愇傪埻偆偙偲偑暘偐傟偽丄偡偖乽億儞僰僉僎乕儉乿偱妝偟傒傑偡丅巹偼偄偮傕帴愇幃偺夝愢戝斦乮俋楬斦乯傪巊偄丄巕嫙偨偪傪敀偲崟偺擇偮偺斍偵暘偗堦庤偢偮丄儕儗乕埻岄乮楢岄乯傪偟傑偡丅嵟弶偼愇傪堦屄偱傕庢偭偨曽乮斍乯偺彑偪偲偄偆儖乕儖偱峴偄傑偡丅
丂愇傪埻偆偙偲偑暘偐傟偽丄偡偖乽億儞僰僉僎乕儉乿偱妝偟傒傑偡丅巹偼偄偮傕帴愇幃偺夝愢戝斦乮俋楬斦乯傪巊偄丄巕嫙偨偪傪敀偲崟偺擇偮偺斍偵暘偗堦庤偢偮丄儕儗乕埻岄乮楢岄乯傪偟傑偡丅嵟弶偼愇傪堦屄偱傕庢偭偨曽乮斍乯偺彑偪偲偄偆儖乕儖偱峴偄傑偡丅| 嘐傾僞儕偲摝偘 |
 丂俆恾偺崟嘆偲懪偭偨忬懺傪傾僞儕偲偄偄傑偡丅師偵崟倎偱敀侾屄傪庢偭偰偟傑偄傑偡傛偲偄偆堄枴偱丄傕偆侾屄懪偰偽憡庤偺愇傪埻傫偱偟傑偆忬懺偱偡丅愇庢傝僎乕儉傪偟偰偄偔偲丄巕嫙偨偪偼丄偩傫偩傫傾僞儕偑暘偐偭偰偒傑偡丅帺暘偱傾僞儕傪敪尒偱偒傞傛偆偵側偭偨巕嫙偼憡庤偺愇傪堦惗寽柦丄捛偄偐偗傑傢偟傑偡丅偦傟傕憡庤偺愇傪庢傞偙偲偵柌拞偵側傝偡偓偰丄帺暘偺愇偑庢傜傟傞偺偑傢偐傜側偄掱偱偡丅壗搙傕愇傪庢傜傟孞傝曉偟偰偄偔偆偪偵丄帺暘偺愇偑傾僞儕偵側偭偰偄傞偙偲偵婥偯偔傛偆偵側傝丄俆恾偺倎偵敀愇傪抲偄偰摝偘傞偙偲傪敪尒偟傑偡丅偦傟傪敪尒偟偨巕嫙偵偼乽乑乑偪傖傫丄偡偛偄偹両愇偺摝偘曽傪敪尒偟偨傛乿偲偦偺応偱偡偖梍傔傑偡丅偦傟傪暦偄偨巕嫙偨偪偼乽偳傟丠偳偙丠乿偲廤傑偭偰乑乑偪傖傫偵嫵偊偰傕傜偄丄帺暘偨偪傕憗懍帋偟巒傔傑偡丅
丂俆恾偺崟嘆偲懪偭偨忬懺傪傾僞儕偲偄偄傑偡丅師偵崟倎偱敀侾屄傪庢偭偰偟傑偄傑偡傛偲偄偆堄枴偱丄傕偆侾屄懪偰偽憡庤偺愇傪埻傫偱偟傑偆忬懺偱偡丅愇庢傝僎乕儉傪偟偰偄偔偲丄巕嫙偨偪偼丄偩傫偩傫傾僞儕偑暘偐偭偰偒傑偡丅帺暘偱傾僞儕傪敪尒偱偒傞傛偆偵側偭偨巕嫙偼憡庤偺愇傪堦惗寽柦丄捛偄偐偗傑傢偟傑偡丅偦傟傕憡庤偺愇傪庢傞偙偲偵柌拞偵側傝偡偓偰丄帺暘偺愇偑庢傜傟傞偺偑傢偐傜側偄掱偱偡丅壗搙傕愇傪庢傜傟孞傝曉偟偰偄偔偆偪偵丄帺暘偺愇偑傾僞儕偵側偭偰偄傞偙偲偵婥偯偔傛偆偵側傝丄俆恾偺倎偵敀愇傪抲偄偰摝偘傞偙偲傪敪尒偟傑偡丅偦傟傪敪尒偟偨巕嫙偵偼乽乑乑偪傖傫丄偡偛偄偹両愇偺摝偘曽傪敪尒偟偨傛乿偲偦偺応偱偡偖梍傔傑偡丅偦傟傪暦偄偨巕嫙偨偪偼乽偳傟丠偳偙丠乿偲廤傑偭偰乑乑偪傖傫偵嫵偊偰傕傜偄丄帺暘偨偪傕憗懍帋偟巒傔傑偡丅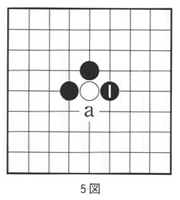
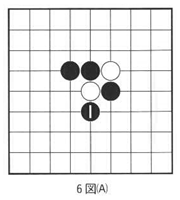
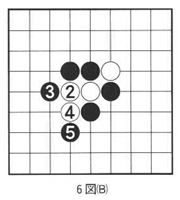
| 嘑拝庤嬛巭偲僐僂丂 |
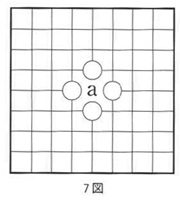
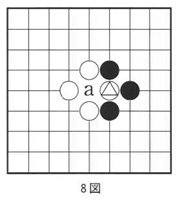
| 嘒恮抧庢傝僎乕儉 |
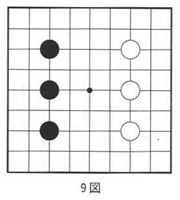
 丂摉慠丄岄偺懪偰傞恖偑嫵偊傞偺偩偲巚傢傟傞偱偟傚偆偑丄岄偺懪偰側偄恖偱傕巕嫙偨偪偵嫵偊傞偙偲偑弌棃傑偡丅尰偵巹偑夢偭偰偄傞梒抰墍丒曐堢墍偺曐曣偝傫払偺傎偲傫偳偼丄岄偑懪偰傑偣傫丅偱傕丄棫攈偵嫵偊偰偄傑偡丅
丂摉慠丄岄偺懪偰傞恖偑嫵偊傞偺偩偲巚傢傟傞偱偟傚偆偑丄岄偺懪偰側偄恖偱傕巕嫙偨偪偵嫵偊傞偙偲偑弌棃傑偡丅尰偵巹偑夢偭偰偄傞梒抰墍丒曐堢墍偺曐曣偝傫払偺傎偲傫偳偼丄岄偑懪偰傑偣傫丅偱傕丄棫攈偵嫵偊偰偄傑偡丅