| 囲碁のルールで厄介なのが、着手禁止です。これをまともに教えようとしても、すぐに理解できる入門者はいないと言ってもいいでしょう。 囲碁は交点のどこにでも置いていいと説明しておきながら、そこは打てないと言えば『囲碁は難しい』と感じ、さらに形は似ているが、相手の石が取れる場合に限り打ってよいなどと話せば、ますます分からないと思われてしまいます。 下表は、呼吸点から見た石を打てる所、打てない所をまとめたものです。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 早見表でわかるように、③の場合だけ石を打てないことになります。 | ||||||||||||||||
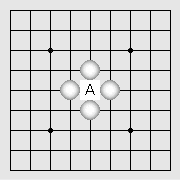 |
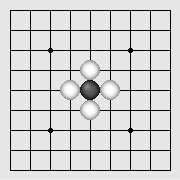 |
|||||||||||||||
| (図10) | (図11) | |||||||||||||||
| (図10)A点に白石は打てますが、黒石は(図11)呼吸点がなく相手の石を取り上げることができないので着手禁止で打てません。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 低学年を指導するユニークなある先生は、着手禁止は打てないとは教えずに、打ってもよいと教えています。 ただし呼吸点がない石は生存できないため、子どもが着手禁止点に打った瞬間に、石を取り上げてしまいます。 『なぜとっちゃうの』と理解できない子どもに『ほら、この黒石は白石に囲まれているよ。囲まれた石はどうなるんだっけ?』こんな会話で納得し始め、2度3度と同じようなことを繰り返すと、石が取られるくやしい経験をすることで、子どもは、もうそこに石を入れなくなります。 子どもたちはこの着手禁止の交点のことを『落とし穴』と言っているそうです。子どもたちが勝手につけたネーミングですが、その穴に落ちたら自爆行為であることがちゃんと分かっているわけです。 この『打ってもよい』ルールのおかげで相手の石が取れる場合に限って打ってよいなどと説明する必要がなくなったそうです。 コウなどのルールや他の技術にも教え方にアイディア・工夫がいろいろありそうですね。 |
||||||||||||||||